【知識ゼロから学ぶ】不動産相続の進め方
親や親戚から不動産を相続する予定だけど「何から手を付けていいかわからない」という方は大半だと思います。まずは不動産相続の流れを大まかに把握しておくだけでも安心です。今回は、不動産を相続する場合の流れを6つのポイントに絞って解説します。
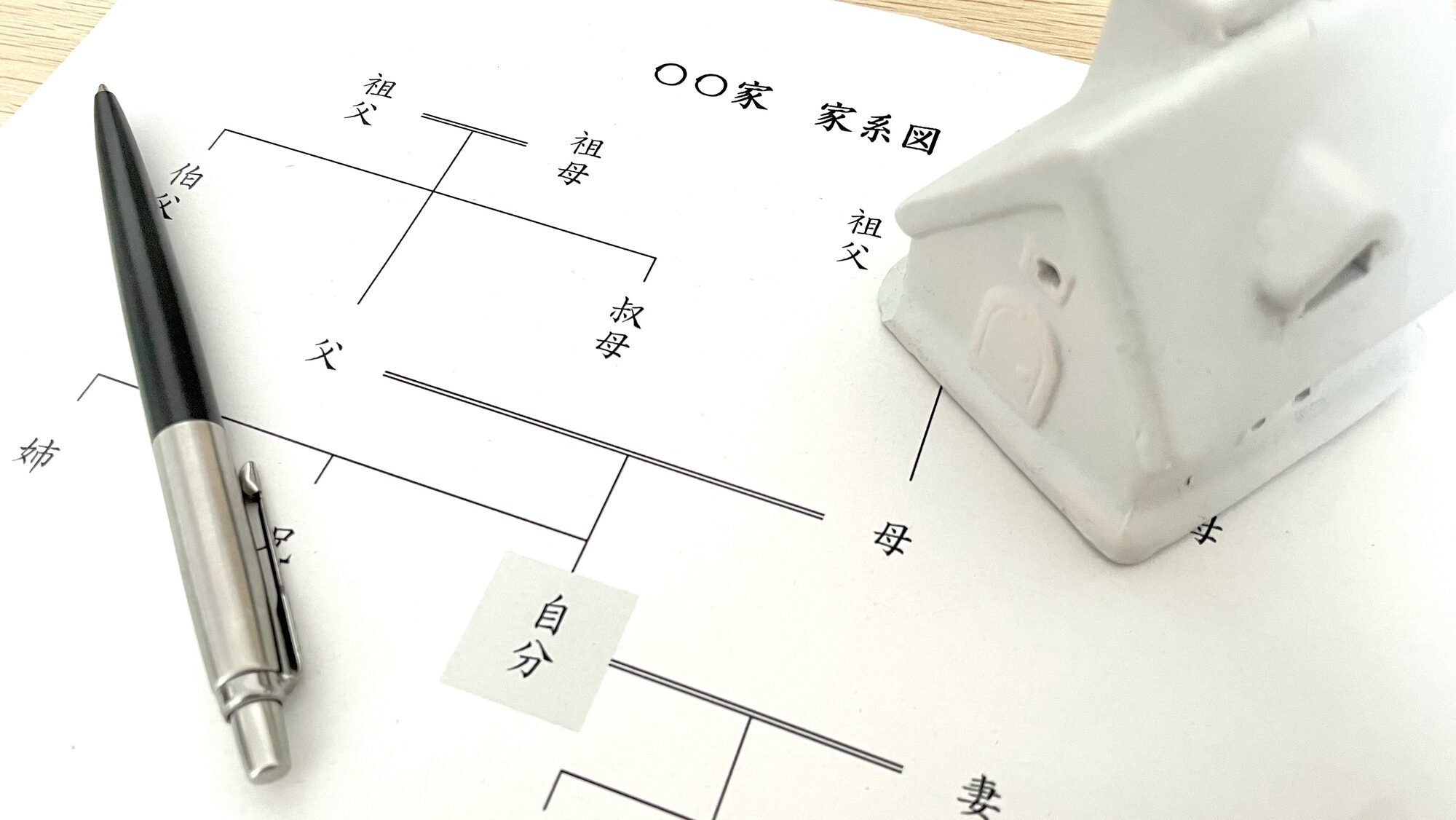
【不動産相続の流れ】6段階の重要ポイント
不動産を相続する場合、以下の6段階が必要になることを覚えておきましょう。
| ①「遺言書」の有無を確認 ②「相続人」を確認する ③「相続財産」がどのくらいか確認する ④「遺産分割協議」を行う ⑤「相続財産の名義変更」+「相続登記」を申請 ⑥「相続税」の申告・納付をする |
優先順位に沿って、それぞれの内容を解説していきますので、必要な確認事項や手続きをイメージしてみましょう。
①「遺言書」の有無を確認
一番大切になるのが「遺言書」です。不動産の所有者が亡くなった場合、どんな手続きよりも先に遺言書の有無を確認する必要があり、「後から出てきた!」とならないよう、よく探しておきましょう。
<遺言書がある場合>
基本的には遺言書に記載されている通りに相続手続きを進めていきます。但し、遺言の種類や保管場所によって、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する「検認」の手続きが必要になる場合があります。
②「相続人」を確認する
遺言書がない場合は、この段階が必要になります。民法で定められた法定相続人が財産を相続することになるので、亡くなった方の戸籍謄本を取得して法定相続人の調査をします。戸籍謄本から、親族関係となる人を全て洗い出し、相続人を確定する必要があります。
遺産分割協議をした後に遺言書が見つかった場合、遺言書の内容が優先されるので注意しましょう。
③「相続財産」がどのくらいか確認する
亡くなった方の財産をすべて確認し「財産目録」の作成します。相続財産に不動産が含まれているかどうかは、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を確認するとよいでしょう。注意点としては、相続財産の総額は、不動産以外のものも含んだすべての遺産総額を算出する必要があることです。
相続財産に借金や未払いの税金などの債務が多く、相続をしたくない場合は「相続放棄」を選択することも可能。相続を知った後3か月以内に、家庭裁判所に書類を提出して、相続放棄の申述手続きを行う必要があります。
④「遺産分割協議」を行う
こちらも遺言書がない場合に必要なもので、相続人が一人も掛けることなく全員で遺産の分割について話し合います。分割内容の合意を得られたら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成して、相続人全員が署名して実印で押印します。
⑤「相続財産の名義変更」+「相続登記」を申請
不動産の相続人が決定したら、不動産の所有権が被相続人から相続人へと移ったことを公示するための手続きとして相続財産の「名義変更」、つまり「相続登記の申請」を行います。相続登記は2024年4月より義務化となっているので、忘れずに行う必要があります。
手続きの際には、登記事項証明書や住民票などの書類を準備し、それを取得するための費用、登録免許税、司法書士に登記を依頼した場合は司法書士への報酬などの費用もかかります。
⑥「相続税」の申告・納付をする
相続財産の総額が、基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合は、「相続税」という税金がかかります。注意すべきは期限があることで、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署に相続税の申告・納付する必要があります。申告期限超過の場合、延滞税が課せられることもあるので早めに支払いを済ませましょう。
不動産相続の手続きは、自分でできるの?
6段階の簡単なポイントをご紹介しましたが、これらの手続きは自分で進められるのでしょうか?
自分以外の戸籍謄本も取得する必要があったり、遺産分割協議書や登記申請書などの必要書類を作成したり…。手間と知識が必要になるので、段取りを組むことや書類作成に苦手意識がある方は、はじめから専門家に依頼すると安心して進められます。
不動産相続の相談は「いえうる窓口」で
不動産会社や司法書士など「それぞれの段階を、誰に相談したらいいのだろう」と相談先を選ぶのも悩ましいものですが、ぜひワンストップですべてを相談できる「いえうる窓口」をご活用ください。
「家を売りたい」「住み替えをしたい」という相談の他にも、「相続した家を売りたい」という相談も多く、不動産相続に関する専門知識や実績があるスタッフや、専門家とも連携して、的確なアドバイスを行っております。お気軽に来店の上、お悩みをお聞かせください。




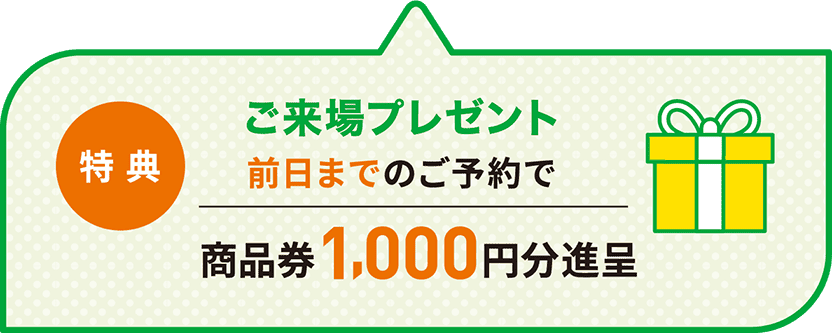
 前の記事へ
前の記事へ 次の記事へ
次の記事へ








